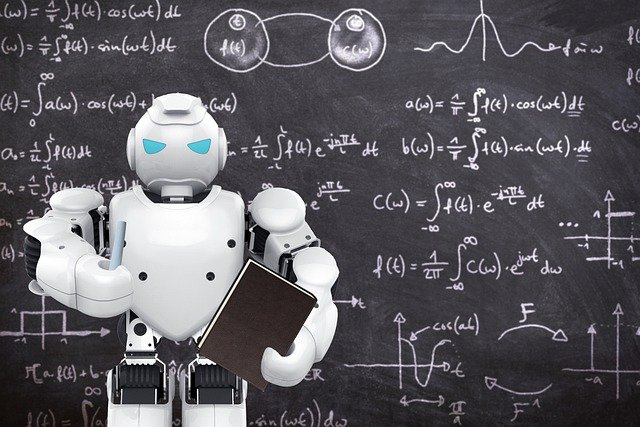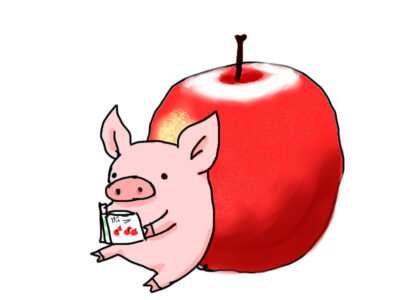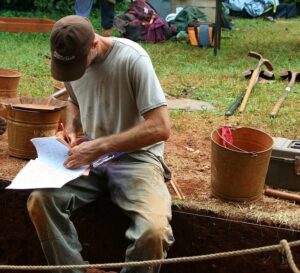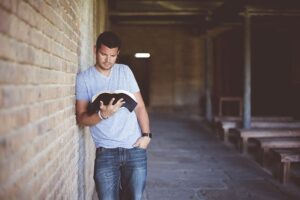不動産投資家のたろーです
この記事では、
- 積算評価と収益還元法はどっちが大事なの?
- 収益還元法ってどう使えばいいの?
という人のために、不動産投資家が積算評価と収益還元法をどう使うべきものか考え方を紹介したいと思います。

で、どっちが大事なの?

一般的には積算評価をベースに考えた方が良いです。実務で収益還元法は使いようがないですし
なぜ積算評価を優先すべきかというと、積算評価の低い物件ばかりを買ってしまうと
- 融資で行き詰まる可能性がある
- 売却したくても売れない可能性がある
といった問題があるからです。

それなら、積算評価の高い物件ばかり買えばいいの?

いや、一概にそうともいえないです
積算評価ばかりを重視すると、収益性が悪くて運営困難に陥ったり、そもそも実際の価格との乖離がある可能性もあります。
そのため、基本的には積算評価をベースで考えつつも、実勢価格や収益性を考えていくべきというのが結論です。

えぇぇ・・もうわけがわからないよ
そこで、本記事では、積算評価と収益還元法とはそもそも何なのか、またどうやって使えばいいのか解説します。
積算評価法
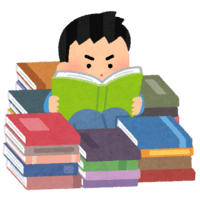

まず、積算評価とは何なのか説明します。
積算評価法は、土地と建物を別々に評価し、その評価額を合算する評価方法のことです。
具体的な計算方法は次のとおりです。
積算評価法の計算式
【計算式】
積算評価=土地の価格+建物の価格
土地の価格=土地面積×①土地の単価
建物の価格=建物の延床面積×②再調達価格×(残耐用年数÷③耐用年数)
積算評価法の計算式に出てくる数値は、以下のようなものを使います。
| 使用するデータ | |
| ①土地の単価 | 相続税路線価 |
| 構造 | ③耐用年数 (法定耐用年数) | ②再調達価格 |
|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート(RC) | 47年 | 20万円/㎡ |
| 重量鉄骨 | 34年 | 18万円/㎡ |
| 木造 | 22年 | 15万円/㎡ |
| 軽量鉄骨 | 19年 | 13万円/㎡ |

なんだかいきなり難しいね

土地の価値に、建物の価値(古くなると価値が下がる)を合わせたものってことです
上記が一般的な考え方ですが、金融機関によって積算評価に用いる土地の単価、再調達価格、耐用年数は変わってきます。
例えば、土地の単価(円/㎡)については、相続税路線価以外にも、公示価格や近隣売買事例に基づく価格なども使われます。
耐用年数についても、法定耐用年数ではなく、ストレスをかけてもう少し短い耐用年数を使っているところもあります。
また、土地の価格については形状による補正や、それぞれの地域や立地等によって補正されて算定されます。
投資家が使うべき評価式と具体的な算定方法
各銀行の評価方法は公開されてはおりませんが、担当者に聞くと耐用年数は何を使うのか、土地の単価は何をベースに考えるのか程度は教えてくれます。
そうはいっても銀行ごとに評価方法も異なっており、それを精緻に再現することもあまり意味がないので、不動産投資家としては相続税路線価をベースに考えておけば基本的には間違いないです。
相続税路線価は、公示価格(≒実際の取引価格に近い)の80%で評価しているので、低めに評価額が算出されます。
ただし、実勢価格と相続税評価額が逆転している地域もあるので、その場合には注意が必要です(銀行によっては価格が逆転していても相続税評価額をベースにして評価しているところもあります)。
相続税路線価は以下のサイトから調べることができます。
全国地価マップ(https://www.chikamap.jp/)
このサイトの相続税路線価等というページから、知りたい場所の住所を検索すると、道路沿いに数字とアルファベットが書かれた地図が表示されます。
例えば、「123E」と記載されていたとき、数字の「123」が相続税路線価を表しており、この場合は123千円/㎡となります。
後ろのアルファベット「E」は借地権割合を表していますが、ここでは意味がないので無視してください。
先ほど見つけた相続税路線価に、知りたい土地の面積をかけると理想的な形状(正方形や長方形)の土地の評価額で算定できます。
実際の土地はきれいな形の土地ばかりではないので、それぞれの形によって補正計算を行います。
なお、土地の補正計算はそれだけで一冊の本になってしまうので、次の本を買って手元においておくと便利です。
路線価による土地評価の実務
色んな土地の形状について計算方法の実例を記載してくれているので、自分が買う土地についてもしっかり計算できます。
不動産投資の実務としては、価格交渉の際にはできる限りに厳密に評価しますが、いろんな物件を見る時はよっぽど特殊な形状でなければ路線価をそのまま使い、敷地延長などの特殊な形状のときには簡単に0.7掛けするなどしてざっくりと評価しておけば十分だと思います。
収益還元法

次は収益還元法の説明です
収益還元法とは、収益性に着目した評価方法のことで、直接還元法とDCF法(ディスカウントキャッシュフロー)の2種類があります。
対象不動産から将来的に生み出される価値を現在価値に割り引いて不動産価格を決定する評価方法です。
以下では、簡便的な直接還元法についてご紹介します。
収益還元法の計算式
収益還元法の計算方法は以下の通りです。
【計算式】
【計算式】
収益還元評価=物件の純収益÷還元利回り
物件の純収益=①年間家賃収入-②諸経費・公租公課等
還元利回り=③地域ごと等に定められた利回り
収益還元法の計算式に出てくる数値は、以下のようなものを使います。
| ①年間家賃収入 | 満室時の80~100% |
|---|---|
| ②諸経費・公租公課等 | 年間家賃収入の20~30% |
| ③地域ごと等に定められた利回り | 統計データ等により参照 例)東京中心部5.5% 地方政令都市7.5% 地方その他都市9.5% |
注意点として、還元利回りは築年数や建物の利用状況などでも補正がなされ、銀行によっても扱いが異なります。
還元利回りの算出方法には、地域ごとに代表的な利回りを使う以外に、販売中の物件の利回りを基にする方法や、不動産会社などが公表しているデータを参考にする方法もあります。
投資家が使うべき評価式と具体的な算定方法
収益還元法については、計算式を見て分かる通り、還元利回りに何を使うのかで大きく数値が変わってしまいます。
同じエリアだったとしても、実際には利回りはかなりの幅を持っています。
そのため、自分で銀行と同じ収益還元法による評価ができるわけがなく、やったところでほとんど意味がありません。

収益還元法って使い道がないの?

知識として知っておけば、指値の根拠などに使えますよ
(参考)収益還元法を指値の根拠にする方法
販売されている物件の利回りが低すぎる場合、収益還元法の評価額を根拠に指値するといった方法があります。
例えば、平均10%の利回りで物件が販売されているエリアで、利回り5%で出ている物件があったときに、「収益還元法で計算すると半額が妥当で、そうしないと融資が通らず誰も買えません」といって指値をします。
もしもともと積算評価で妥当な金額の物件だったときには、積算評価を下回る価格で買えるので、銀行からの評価がかなり高くなります。

こういった方法を不動産のアービトラージ(価格差を利用した取引)といいます
積算評価と収益還元法のどちらを重視するべきか


評価方法はわかったけど、結局どうしたらいいの?
重視すべきは積算評価法!
基本は積算評価を重視した方が良いです。
もともと収益還元法は、積算評価法だけでは実態と乖離してしまう物件の価値を、適切に評価できるように採用したという経緯があります。
銀行や融資商品によってもどちらの評価方法を用いるのか(重視するか)は異なっており、色んな金融機関へ実際にヒアリングをしてみると、
- 積算評価法のみで判断する
- 積算評価法と収益還元法の低い方を採用する
- 積算評価法がメインで収益還元法は参考として使う
など、細かい評価方法は各金融機関で様々で、収益還元法を重視している金融機関もあります。
きらぼし銀行は、東京23区の場合は積算が参考値となり、原則
— 紺野健太郎/KENTARO KONNO (@KentaroKonno) August 1, 2020
収益還元で評価する事になるので、積算弱くても収益還元で評価が出る可能性もあります。積算と収益還元の間で悩む不動産投資家は多い、あとは各々の投資戦略次第。
しかし、どちらかというと積算評価法を重視し、収益還元法を補助的に利用している金融機関の方がやはり多いです。
もし積算評価の全くでない物件であっても、物件を持ち込んだ金融機関が収益還元法を重視しているのであれば、その金融機関を使えば融資を受けられます。
しかし、その収益還元法で融資を受けた物件を売却しようとすると、やはり積算評価が出ないので、次の買主も売却時には同じく収益還元法で評価してくれる金融機関を使わないと融資を受けられません。
したがって、収益還元法のみで物件を買ってしまうと物件売却という投資の出口が困難になる可能性があります。
また、収益還元法をメインで評価しない金融機関からすると、積算評価が出ないことが原因で債務超過となってしまい、次の融資が困難になる可能性もあります。
信用棄損には大きく分けて3種類あります
— みどり🍄不動産投資ビギナーへのアドバイスしています (@35FIRE3) July 14, 2022
▶️収益評価<借入金
耐用年数を超えた場合に収益を0と判定することも
▶️積算評価<借入金
築年数によって建物評価は0に近づきます
▶️残法定耐用年数<融資期間
銀行の評価方法やルールによって異なりますが、
上手く回避していくことで規模拡大につながります
銀行融資を使ってプロパーで融資を考えると収益還元の銀行もあるが、殆どが積算評価を主体に銀行評価する。
— フォーニッツ おおやま @神奈川、不動産賃貸 (@_fornits_) September 5, 2022
何が言いたいかと言うと、収益還元でみる銀行からばかり融資を引くと、大部分が積算でみるから、その先で圧倒的に自己資金がある場合は別として、融資が続かなくなると個人的に思う。
取引銀行2行に「保有する金融資産で不動産を買うと評価が下がるのか?」を聞いてみた。
— モーガン@不動産投資家 (@tsukubanosorani) November 20, 2018
1行は不動産を固定資産税評価額で資産として評価する。もう1行は路線価(積算評価)だった。
収益還元法の高値で買うとそのギャップ分で、セミリタイア到達まで融資を引き続けられなくなるかも。
積算評価は万能ではない!

それなら積算評価の高い物件を買えば間違いないね!

それは違います!
積算評価が高かったとしても、
①実勢価格と逆転している
②収益性が全くない
となれば、大失敗する可能性があります。
注意① 実勢価格と逆転している
都市部は積算評価に比べて実勢価格が高く、積算評価が過小評価になりがちですが、地方部へ行くと実勢価格よりも積算評価の方が高いエリアもあります。
積算評価が1,000万円あるからお買い得だと思っても、そのエリアで実際に取引されている価格が500万円であれば、売却しようとしたときには500万円でしか売れません(知らずに買う投資家がいれば別ですが)。
資産性は積算価格が1つの目安🙂
— はじじん (@haji797) August 25, 2021
積算評価は金融機関が物件評価としてみる場合も多くモノサシの目安として分かりやすいものです。
都心部に向かうほど実勢価格と積算評価の価格差が大きく、地方によっては実勢価格と逆転することもあるのでエリア感の感覚は必要です。
注意② 収益性が全くない
次の問題点としては、積算評価が高いからといっても、物件の収益性が低ければ事業運営は成り立ちません。
物件の収益性が悪く、家賃収入がほとんど残らない(もしくは支出が多い)状態であれば、売却するまではほとんど手元にお金が残らず、給料などから補填する状態になってしまいます。
不動産投資では
— ホセヒデ|不動産・事業・営業 (@adventierra) January 14, 2022
積算評価する銀行が多くて
積算が出る=銀行評価が出る=融資が出る
→「利回り低くても買う!」人いるけど
👺マジで危険
・積算出てる=固定資産税高い
・積算出てる=築古多い=修繕かかる
収益性低いけど銀行が担保取れるだけの物件買って自分に何のメリットあるか考えた?笑
バランス感覚が重要!

話をまとめると、積算評価が高くて、収益性も高くて、売却時に高く売れる物件を買えばいいってこと?

そんな物件があればです
不動産投資の理想の物件と言えば、
- 積算評価が高い
- 収益性が高い
- 価格が安い
といった物件ですが、そんな物件は誰もが欲しいので、投資家にすら回ってきません(不動産会社が買取してます)。
不動産投資は毎年家賃収入が入ってくるので、高く購入してしまったとしても、長期間保有していればその分の家賃収入を早くもらえるので、買わないよりかは買った方がよくなるケースも多いです。
そのため、積算評価の重要性も考慮しつつ、バランスを見ながらどこかで妥協することも必要です。
まとめ
本記事では、積算評価と収益還元法について紹介しました。
要点をまとめると、
- 積算評価をベースに考えることで、①長期的に信用棄損になりにくい、②売却しやすいといったメリットがあります。
- ただし、実勢価格を考慮しないと売却は不可能であり、収益性を考慮しないと運営不可能となるので、バランス感覚も大事です。
- 収益還元法は、投資家の判断基準としてはほとんど役立ちませんが、物件購入の場面などで収益還元法が使える場面もあるので、評価方法は理解しておくと良いです。

うーん、バランス感覚って難しいね

こだわりすぎないことも重要ですよ